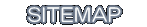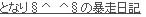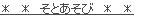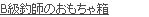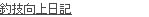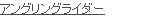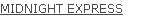2010年01月30日
見かけるようになった管釣りベイト【ブーム?】
始めた頃には異色だった管釣りベイト
2005~2006年にかけて近所のトラウト管理釣り場に行くようになったのだが、当時ベイトタックルなんて持ってる人はほとんどおらず、私は正に異色の存在そのものだった。

近頃めっきり行く機会は減ってしまったが、
行けば必ず『ベイトタックル』を持っている人を見かける。
よく行ってた時期もブログでも段々と『管釣りでベイト!』が増えていたから、「もしかすると現場で見かけるかも?」と多少の期待を持ちながら釣り場に行ったこともあった。
軽量キャストが要求される管理釣り場で、バスロッド+ベイトリールを持ち込むのは結構な勇気がいることだ。
バックラッシュで釣りにならないかもしれない。
更にそれなりに目立ってしまう。(釣れてもバックラッシュでもw)
・・・あげれば色々出るだろうがこれくらいにしておこう。
だから始めた頃の個人的予測では、
管釣りベイトは「滅ぶ」と思っていた。
当時、他に知ってる『管釣りでもベイト』は、Eight_Worksさんの
ベイトキャスティング フェチ!! だけだったからね!
メーカーの管釣りベイト戦略
国内大手二大メーカーであるshimanoとDaiwa、それぞれに管釣りベイトタックルを展開していた。
shimanoはカルカッタ・コンクエスト50S/51S+カーディフ・ベイト。
Daiwaはリベルト・ピクシー(プレッソ)+プレッソ・ベイト。
雑誌やらWebサイトを見た限り、それなりに宣伝もしていたように見えたし釣具店でも普通に見かけた。
だけど釣り場では見かけなかった。
管理釣り場の主となるメソッドが、マイクロスプーンのスローリトリーブ。
もしくはボトムでコツコツ小さく動かすボトチョン・メソッド。
これだとベイトリールを使う意味を見出す事自体がとても困難なのだ。
スピニングの最大の長所は容易なキャスト。
ライントラブルは誰にとっても嫌なものであるし、ルアーが軽量級なら余程の好き者でない限りスピニングでやるだろう。
昔欠点だった巻き上げ力や糸ヨレも、許容範囲と言えるくらいに克服してて最大の欠点なんて言えるものは無くなっている。
だがスピニングが容易なキャストと引替えに失ったものはある。(構造的に)
それはルアーをアクションさせる「動く!止める!」の動作が緩慢なこと。
言い換えれば、ハンドルを一定スピードで巻く、ハンドルを止めたままにするというメソッドならば、そんな欠点は露呈しない。
管理釣り場向けに売られているルアーのほとんどが、巻き続けるか、止めて使うかのどっちかだから、それを欠点と思う人がいないんだろうけど。
上記メーカーのロッド含め、他にも管釣り用と銘打ったロッドはあった。
その多くが、2g~のスプーンが投げられますよ。という、
「柔らかくしたから取りあえず投げるの頑張って下さい」
という感じの消極的なコピーが目についた。
折角リールが「動く!止める!」をキビキビできる長所があるのに、セットするロッドがデローンとしてたら・・・楽しくないでしょう?(笑)
ルアーを意図的にアクションさせるのが目的だから、スプーン云々書かれたロッドには遂に手が伸びなかった。
ベイトタックルの有用性 【トラウト管理釣り場】 なんてのも書いたっけ。
メーカーの管釣りベイト戦略が万人向けのリスクを抑えたコンサバで消極的なのは仕方なしか?
絶滅危惧種相手にリスクを抑える・・・・。
管釣りベイトは「滅ぶ」と思った。
思ったようなベイトロッドがない悩み
2007年に始まった ベイトでいこう!のyou-youさんに出会って流れが変わった。
(引用)----------------------------------
そんな訳で1gが投げられて3lbが使える
EXファーストのロッド・・・
そんな夢のようなロッド・・・
だれかご存知ありません!?
-------------------------------------------------
そうつぶやく彼に共感を覚えた。
そうそう、そういうしっかり曲がって尚かつシャープな
・・・そんなのあるんかいっ!(笑)
思ったようなロッドがないためなのか?胴掛スタイルほぼ完成!というタイトルで書かれた彼の記事を腹を抱えて笑って読んだ。
すると、その4日後に、私の F0-60X ELESEがボキッと折れた。
これは果たして偶然だったのか?神様のイタズラならば、「さすが神様!」と頭を垂れたい(笑)
折れなきゃ不自由ながらもELESEで我慢しただろう。
ルアーはコツさえ掴めばバスロッドでも何とかなる1/8~3/16ozのトップウォーター・プラグ。
求めていたのはベリーがグイグイ曲がって、アクションするときに穂先をきちんとコントロールできるロッド。
ペンシルなんかはルアーの抵抗が小さいから竿がスローだとルアーが動きすぎてしまう。
小さなTWルアーをアクションさせて
喰わせの駆け引きも可能なロッド・・・
そんな夢のようなロッド・・・
ここのお店にありますか?
今度は私がロッドを探す番だった。しかも店頭で唐突にw
ブランクを扱っている釣具店で色々触って
勘だけで選んだのは、JustaceのSFT631L 。

細さの雰囲気はバス用のウルトラライト・スピニング。
ガイドが付いていない竿の元(ブランク)は、その硬さ速さの評価がとても難しく、もしかしたら全然ダメかも?と思うくらいにシャキシャキしてた。
後から見たらブランクのカテゴリーにエリアロッドはあったが
管釣り(エリア)ベイトはどこにもなかった。
さほど時を置かずyou-youさんのオリジナルロッド=ベイスペが登場し、uedaさんのクワトロベイト、番長さんの番長スティック、magさんの自作いっぱい!、Eight_worksさん+雨蛙氏ブランクのコラボロッド、とても紹介しきれない数のオリジナルな管釣りベイトロッドをblogで堪能させていただいた。
そのどれもが各人のコダワリと変態ぶりを楽しませてくれる個性たっぷりな逸品であった。
自由で勝手にベイト難民村(自虐行為か?)
発想の転換は心を軽くしてくれる。
あると思って探すから無くてイライラするのだ。
元々無いと割り切って
自由気ままに発想して勝手に作ればそれでいいと。
それなら誰も、メーカーすらも責めずに済む・・・
キッカケはここのコメント欄。
管釣りベイトの王道!というのはおふざけなのか?それとも自虐なのか?が微妙でクスクス笑っていたが(笑)、中にはまじめに受けて感じ悪く思った人もいて・・・閃いた!!
俺たちきっと難民の王子!!(笑)
すぐにベイト難民村の下書きを書いてyou-youさんにメールした。
くくりは遊び心のみでタックル仕様も対象魚すら問わないスタイルでどうかな?と。
どんどん悪ノリして、楽しそうに管釣りでもベイトで遊んじゃうようなアングラーを勝手に難民認定してリンクしちゃおう!という無謀さ(笑)
無謀な荒療治したら・・・やっぱ滅びるか?
勝手に認定された!というクレームは今のところはありません。
それから月日が過ぎて・・・・
2大メーカーのカタログぐらいは目を通したりもしたが、釣り雑誌は一切読まず、お気に入りのブログを読むだけの日々を過ごした。
無謀な荒療治はキッカケになって、有志が晩夏の琵琶湖で泊まりがけのオフ会まで開催してくれた。
自身は管理釣り場に遊びに行く頻度が減ってしまい、それについての新しい発見やメソッドは無いんだけど、行けば良く見るようになったのは、
「ベイトタックルで遊ぶ人」。
不思議に思ってblogを広く見回してみたら・・・・
思ったよりずっと多くの人が、
管釣りベイトを自由な発想で楽しんでいた!(驚)
それぞれが思ったようなロッドが手に入るような時代になった?
ブログ活動をしていない間に何かがあった?
それまで情報不足でトライしにくかっただけ?
ベイトタックルって何だか楽しいんだよね!
いずれにせよそう思っている人がベイトを持ち込んでいると思う。
バスでは普通なんだけど、管理釣り場に行くと海外で日本人を見つけたような・・・そういう感覚に陥る。
さらに驚いたのは新型管釣りベイトリール(カーディフ50SDC)が登場したことだった。
なんせ滅びゆくものと思っていたのだ。
個人の遊びと違い、大メーカーが多大な開発費を投じたであろうことは、商品のそれなりの値段からも察しが付くが、DCブレーキ導入というshimanoの粋な計らいには賛辞を送りたい。
リールはあるけど思ったような竿がない・・・ってな実態は多分すぐには変わらない。
けれど、用意されたモノがないからって
楽しみ方は滅びない・・・。
そう思えるようになったってのが、最近の管釣りベイトへの感想なのだ。
2005~2006年にかけて近所のトラウト管理釣り場に行くようになったのだが、当時ベイトタックルなんて持ってる人はほとんどおらず、私は正に異色の存在そのものだった。
近頃めっきり行く機会は減ってしまったが、
行けば必ず『ベイトタックル』を持っている人を見かける。
よく行ってた時期もブログでも段々と『管釣りでベイト!』が増えていたから、「もしかすると現場で見かけるかも?」と多少の期待を持ちながら釣り場に行ったこともあった。
軽量キャストが要求される管理釣り場で、バスロッド+ベイトリールを持ち込むのは結構な勇気がいることだ。
バックラッシュで釣りにならないかもしれない。
更にそれなりに目立ってしまう。(釣れてもバックラッシュでもw)
・・・あげれば色々出るだろうがこれくらいにしておこう。
だから始めた頃の個人的予測では、
管釣りベイトは「滅ぶ」と思っていた。
当時、他に知ってる『管釣りでもベイト』は、Eight_Worksさんの
ベイトキャスティング フェチ!! だけだったからね!
メーカーの管釣りベイト戦略
国内大手二大メーカーであるshimanoとDaiwa、それぞれに管釣りベイトタックルを展開していた。
shimanoはカルカッタ・コンクエスト50S/51S+カーディフ・ベイト。
Daiwaはリベルト・ピクシー(プレッソ)+プレッソ・ベイト。
雑誌やらWebサイトを見た限り、それなりに宣伝もしていたように見えたし釣具店でも普通に見かけた。
だけど釣り場では見かけなかった。
管理釣り場の主となるメソッドが、マイクロスプーンのスローリトリーブ。
もしくはボトムでコツコツ小さく動かすボトチョン・メソッド。
これだとベイトリールを使う意味を見出す事自体がとても困難なのだ。
スピニングの最大の長所は容易なキャスト。
ライントラブルは誰にとっても嫌なものであるし、ルアーが軽量級なら余程の好き者でない限りスピニングでやるだろう。
昔欠点だった巻き上げ力や糸ヨレも、許容範囲と言えるくらいに克服してて最大の欠点なんて言えるものは無くなっている。
だがスピニングが容易なキャストと引替えに失ったものはある。(構造的に)
それはルアーをアクションさせる「動く!止める!」の動作が緩慢なこと。
言い換えれば、ハンドルを一定スピードで巻く、ハンドルを止めたままにするというメソッドならば、そんな欠点は露呈しない。
管理釣り場向けに売られているルアーのほとんどが、巻き続けるか、止めて使うかのどっちかだから、それを欠点と思う人がいないんだろうけど。
上記メーカーのロッド含め、他にも管釣り用と銘打ったロッドはあった。
その多くが、2g~のスプーンが投げられますよ。という、
「柔らかくしたから取りあえず投げるの頑張って下さい」
という感じの消極的なコピーが目についた。
折角リールが「動く!止める!」をキビキビできる長所があるのに、セットするロッドがデローンとしてたら・・・楽しくないでしょう?(笑)
ルアーを意図的にアクションさせるのが目的だから、スプーン云々書かれたロッドには遂に手が伸びなかった。
ベイトタックルの有用性 【トラウト管理釣り場】 なんてのも書いたっけ。
メーカーの管釣りベイト戦略が万人向けのリスクを抑えたコンサバで消極的なのは仕方なしか?
絶滅危惧種相手にリスクを抑える・・・・。
管釣りベイトは「滅ぶ」と思った。
思ったようなベイトロッドがない悩み
2007年に始まった ベイトでいこう!のyou-youさんに出会って流れが変わった。
(引用)----------------------------------
そんな訳で1gが投げられて3lbが使える
EXファーストのロッド・・・
そんな夢のようなロッド・・・
だれかご存知ありません!?
-------------------------------------------------
そうつぶやく彼に共感を覚えた。
そうそう、そういうしっかり曲がって尚かつシャープな
・・・そんなのあるんかいっ!(笑)
思ったようなロッドがないためなのか?胴掛スタイルほぼ完成!というタイトルで書かれた彼の記事を腹を抱えて笑って読んだ。
すると、その4日後に、私の F0-60X ELESEがボキッと折れた。
これは果たして偶然だったのか?神様のイタズラならば、「さすが神様!」と頭を垂れたい(笑)
折れなきゃ不自由ながらもELESEで我慢しただろう。
ルアーはコツさえ掴めばバスロッドでも何とかなる1/8~3/16ozのトップウォーター・プラグ。
求めていたのはベリーがグイグイ曲がって、アクションするときに穂先をきちんとコントロールできるロッド。
ペンシルなんかはルアーの抵抗が小さいから竿がスローだとルアーが動きすぎてしまう。
小さなTWルアーをアクションさせて
喰わせの駆け引きも可能なロッド・・・
そんな夢のようなロッド・・・
ここのお店にありますか?
今度は私がロッドを探す番だった。しかも店頭で唐突にw
ブランクを扱っている釣具店で色々触って
勘だけで選んだのは、JustaceのSFT631L 。
細さの雰囲気はバス用のウルトラライト・スピニング。
ガイドが付いていない竿の元(ブランク)は、その硬さ速さの評価がとても難しく、もしかしたら全然ダメかも?と思うくらいにシャキシャキしてた。
後から見たらブランクのカテゴリーにエリアロッドはあったが
管釣り(エリア)ベイトはどこにもなかった。
さほど時を置かずyou-youさんのオリジナルロッド=ベイスペが登場し、uedaさんのクワトロベイト、番長さんの番長スティック、magさんの自作いっぱい!、Eight_worksさん+雨蛙氏ブランクのコラボロッド、とても紹介しきれない数のオリジナルな管釣りベイトロッドをblogで堪能させていただいた。
そのどれもが各人のコダワリと変態ぶりを楽しませてくれる個性たっぷりな逸品であった。
自由で勝手にベイト難民村(自虐行為か?)
発想の転換は心を軽くしてくれる。
あると思って探すから無くてイライラするのだ。
元々無いと割り切って
自由気ままに発想して勝手に作ればそれでいいと。
それなら誰も、メーカーすらも責めずに済む・・・
キッカケはここのコメント欄。
管釣りベイトの王道!というのはおふざけなのか?それとも自虐なのか?が微妙でクスクス笑っていたが(笑)、中にはまじめに受けて感じ悪く思った人もいて・・・閃いた!!
俺たちきっと難民の王子!!(笑)
すぐにベイト難民村の下書きを書いてyou-youさんにメールした。
くくりは遊び心のみでタックル仕様も対象魚すら問わないスタイルでどうかな?と。
どんどん悪ノリして、楽しそうに管釣りでもベイトで遊んじゃうようなアングラーを勝手に難民認定してリンクしちゃおう!という無謀さ(笑)
無謀な荒療治したら・・・やっぱ滅びるか?
勝手に認定された!というクレームは今のところはありません。
それから月日が過ぎて・・・・
2大メーカーのカタログぐらいは目を通したりもしたが、釣り雑誌は一切読まず、お気に入りのブログを読むだけの日々を過ごした。
無謀な荒療治はキッカケになって、有志が晩夏の琵琶湖で泊まりがけのオフ会まで開催してくれた。
自身は管理釣り場に遊びに行く頻度が減ってしまい、それについての新しい発見やメソッドは無いんだけど、行けば良く見るようになったのは、
「ベイトタックルで遊ぶ人」。
不思議に思ってblogを広く見回してみたら・・・・
思ったよりずっと多くの人が、
管釣りベイトを自由な発想で楽しんでいた!(驚)
それぞれが思ったようなロッドが手に入るような時代になった?
ブログ活動をしていない間に何かがあった?
それまで情報不足でトライしにくかっただけ?
ベイトタックルって何だか楽しいんだよね!
いずれにせよそう思っている人がベイトを持ち込んでいると思う。
バスでは普通なんだけど、管理釣り場に行くと海外で日本人を見つけたような・・・そういう感覚に陥る。
さらに驚いたのは新型管釣りベイトリール(カーディフ50SDC)が登場したことだった。
なんせ滅びゆくものと思っていたのだ。
個人の遊びと違い、大メーカーが多大な開発費を投じたであろうことは、商品のそれなりの値段からも察しが付くが、DCブレーキ導入というshimanoの粋な計らいには賛辞を送りたい。
リールはあるけど思ったような竿がない・・・ってな実態は多分すぐには変わらない。
けれど、用意されたモノがないからって
楽しみ方は滅びない・・・。
そう思えるようになったってのが、最近の管釣りベイトへの感想なのだ。
あほあほルアーマンの この記事のつづきを読む
2010年01月17日
黄色のPixy+偽バンタム・インプレ【フィーリング】
ふわっと握ってブランクを振る竿
ブランクスルーのリールシートを使い始めたときは、グリップが真っ直ぐであることに恩恵を覚えた。
力んで投げても右に行かない。
陸っぱり少年の意地とプライドに『誰よりも遠くで魚を掛けたい』というチカラ勝負な部分がある限り、ブランクスルーで真っ直ぐなリールシートの方が、力のこもったスイングを受け止めてくれた。
年月を経て、あれれ?なおじさんになった今になって想い出すのは、大昔のカッチョエータックルを持ったおじさん達は、もっと軽く、全く力まないで、ふわっとしたスイングで充分な飛距離を出していたことだ。
同じ事柄を、筋力じゃなく技で解決できるならそっちがスマートだ。
この角度が『あえて』つけてある意味はきっとリールの高さ以外にも・・・

この竿はグリップを力一杯 わしづかみしちゃうと右に飛ぶ。
コツはブランクの中心線を意識して、スイングと共にねじられていくグリップを小指の握り加減で綺麗に振ってあげること。
ふわっと握って振り始めたら、スッと小指に力を入れていき、最後にピタリと竿先を止めてあげるのだ。
王禅寺、最初の1時間
今年のトップウォーター・パターンはどうだろうか?
そんな期待と不安の混じったお出かけ前の気持ちとは裏腹に、見た目の状況はあまりにも平穏だった。
14:25、晴天、風無し、ライズも・・・なし(clickで拡大)

いきなり遠くに投げるようなことはしない。
久しぶりに軽量キャストをするんだから、メカニカルブレーキとマグVブレーキを調整しつつ、PEラインに適度な湿り気を与え、自身の感覚を呼び起こすところから始めた。
サミー65 白、・・・全くもってキャストのみ良好(笑)。
マグブレーキのダイアルだけが決まった(4~5)
さてさて、もう全然分からない状況。
シケイダーで状況の整理から始めることにする。
普通のリトリーブ、早めのリトリーブ、リトリーブ中にアクションを追加。
三角波の先頭に虚しく羽ばたくシケイダー・・・。
スローに引いていくとポツリと空かしバイトが・・・、哀れ・・・(悲)
人の悪いばるたんさんが、この哀れなバイトを車から見た!と、
とてもタイミング悪く登場、計算だろうか?
ところで、シケイダーを投げていて気が付いたが、ガングリップの竿には意外なくらいマグVブレーキは感じが良い。
強く握らないでふわっと投げるキャストだと、スプールを加速している時間はビュンと投げるときの倍くらいはある感じ。
リリースから振り込んでいる間の竿が踏ん張れる感じが遠心ブレーキよりあるため『長く持っていられる感』が飛距離を生んでくれる。
シケイダーのブレーキは(5.5)、小刻みにブレーキ設定を変えられる気安さは安心感。
ブレーキダイアルの方向が、スコーピオンMgと逆で強くしようとして弱めたり・・・ってな失敗はあったが気付けば後は問題なし。
ブランクスルーの竿でマグVに感じていたモッタリ感や最後の伸びの無さは、飛距離を得ようとブンブン振るためにブレーキ設定が強めだったことも関係しているようだ。
今回は長く持ったようなスイングでじっくりと回転を上げるから、ブレーキ弱めでもキャスト直後のバックラッシュとは無縁。
その上弱めのブレーキ設定はマグのモッタリ感を弱め、キャスト後半はPEラインの風流れを押さえてくれて微妙なサミングもほとんどしなくて済んでしまう。
遠心とマグVのキャラクターの違いと言えばそれまでだが、
有効な活用法が今まで見えなかっただけにこれは収穫。
釣果の収穫は全然無いので、ルアーチェンジを繰り返しているとキッカケになるルアーが遂に出た。

イエローマジック 6cm (7gくらい)
ポコン、ポコン、とポップしていくとバイトが増え、
それに釣られたかのように周囲はライズの嵐に!!!
多少喰うには良くない大きさなのか?ヒットにはつながら無いが、魚たちの注意を一気に水面に引きつけた。
ファーストフィッシュまでの時間とゲームの時間
そこでDUELのチビポッパーに切り替えるとようやくヒット!
15:14、待望のファーストフィッシュ!

スタートから約50分!!
魚のたんまり入った管理釣り場で一尾を釣ると言う意味では、
『ずいぶんと長い時間だ。』
普通の人ならトップウォーター・プラグなんてとっくに諦めて
自信のある他のルアーを投げるだろう(笑)
「たった一匹釣るのにそんなに時間をかけて、
残り2時間ちょっとで何匹釣れるのさ?」
至って合理的な質問だろう。
「今日はこの一匹で終わりかも?(笑) わはは!」
今ならそう笑って答えられる。
他のルアーならともかく誰も投げていないようなルアーはここからが違う。
注意を一端水面に向けることさえ出来れば、そこからはかなり余裕で釣り続けられる事が多い。
ポップに激しくリアクションするのを確認して追試をしていく。
こうなると、2連続、3連続は当たり前。

他のルアーの適合具合を試し、本当にポップが良いか?を更に確認。
釣れたのは全部25cmくらいのニジマスOnly。
短く強いポップ、動く!止める!がハッキリするほどリアクションも強くなった。

ただし、明らかに釣れるようになるとゲームは終わり。
別に時間が来たワケじゃなく、30分も釣れ続ければゲームは段々と漁獲作業に近くなってしまうからだ。
最初の一匹を期待したあの感じはどこかに消える。
池がリセットされて初めて訪れた王禅寺だったが、実を言えば今回のパターンは旅人さんの釣行記から多少の予想はしていた。
同じ時間帯にほとんど同じ手順で進めたとはいえ、ルアーやアクションのパターンについては全く同じ結果に嬉しくなった。
特殊なスタイルで他の情報が当てにならないと書いたこともがあったが、それは既に遠い昔のことのようだ。
黄色のPixy+偽バンタムのフィーリング
キャストに関してはタックル自体が羽のように軽く、おかげで握りしめること無しにゆったり振れるバランスは、今までの組み合わせの中では抜群と言っても良い。
自己基準に「あれれ?」とマッチしてる
ヒット~フッキングの間に影響するギヤ比(1:5.8)も、ミリオネアST-1000(1:5未満)やカルカッタ50XT(1:5.0)からすると、忙しくなく25cmのトラウトが引っ張られてしまう分を充分に巻き取ってくれた。
竿でためすぎると口切れするのか?
竿をグイグイ曲げてやるとこれでもか!?というほどバラシを連発したが、竿の良い角度を見つけてこちらも解消。
作成時にニューガイドコンセプトとは異なるガイド間隔(曲げたい箇所を作るため)を設定した分、曲げすぎるとラインの角度が強くなる部分が効率を落とし、ある程度曲がるとハンドルからの入力でドラグが滑りやすいが、偽ELESEと同じブランクでもっと曲げたい設計思想なのでそこは仕方なし。
ELESEから始まりパワーを落とした偽ELESEの2つは、TBSリールシートを深く握ってブンブン振れるタックルだったが、ある意味力んで投げますよ!って前提からは逃れられなかった。
ブランクスルーのリールシートしかり、ニューガイドコンセプトしかり、ブランクのパワーを余すところ無く引き出す思想は、方向に関するコントロールをキッチリさせて、細身の軽いブランクを攻撃的に仕上げてくれた。
結果スイングを速くすることができて軽量系の飛距離は伸びたが犠牲にした部分もある。
利点ばかりを追っていたら、いつしかリリースポイントは限定的でルアー飛翔速度が速くて飛んでいる間が忙しい・・・という釣果を追うことばかりに向いた心理的な余裕を失っている部分。
黄色のPixy+偽バンタムのフィーリングは、まさしく今まで余裕の少ない自分を見直すだけの感触を与えてくれた。
ほんの5%くらいの飛距離と引き替えに、
力まずゆったり振れるための良さ。
リリースポイントが広いおおらかさ。
ゆっくり飛ぶ分サミングの緊張感の少なさ。
軽量トップウォーター・ゲームを楽しむための要素は、釣ること意外にもフィーリングを楽しむ部分はあると思う。

パターン構築プロセスも更にゆる~く楽しめそうです!
<最後に>
お忙しいところ現場まで見にきてくれたばるたんさん、いつもありがとう!
事前にアクションパターンを書いて下さった旅人さんに感謝!
そして、長文をいつも読んでくださるみんなに感謝!!
ほんとうにありがとう!
※ あくまで自己基準の旧式な仕様ですので、ブランクスルーでスタートした方には角度のあるグリップは相当の違和感があると思われます。
ブランクスルーのリールシートを使い始めたときは、グリップが真っ直ぐであることに恩恵を覚えた。
力んで投げても右に行かない。
陸っぱり少年の意地とプライドに『誰よりも遠くで魚を掛けたい』というチカラ勝負な部分がある限り、ブランクスルーで真っ直ぐなリールシートの方が、力のこもったスイングを受け止めてくれた。
年月を経て、あれれ?なおじさんになった今になって想い出すのは、大昔のカッチョエータックルを持ったおじさん達は、もっと軽く、全く力まないで、ふわっとしたスイングで充分な飛距離を出していたことだ。
同じ事柄を、筋力じゃなく技で解決できるならそっちがスマートだ。
この角度が『あえて』つけてある意味はきっとリールの高さ以外にも・・・

この竿はグリップを力一杯 わしづかみしちゃうと右に飛ぶ。
コツはブランクの中心線を意識して、スイングと共にねじられていくグリップを小指の握り加減で綺麗に振ってあげること。
ふわっと握って振り始めたら、スッと小指に力を入れていき、最後にピタリと竿先を止めてあげるのだ。
王禅寺、最初の1時間
今年のトップウォーター・パターンはどうだろうか?
そんな期待と不安の混じったお出かけ前の気持ちとは裏腹に、見た目の状況はあまりにも平穏だった。
14:25、晴天、風無し、ライズも・・・なし(clickで拡大)

いきなり遠くに投げるようなことはしない。
久しぶりに軽量キャストをするんだから、メカニカルブレーキとマグVブレーキを調整しつつ、PEラインに適度な湿り気を与え、自身の感覚を呼び起こすところから始めた。
サミー65 白、・・・全くもってキャストのみ良好(笑)。
マグブレーキのダイアルだけが決まった(4~5)
さてさて、もう全然分からない状況。
シケイダーで状況の整理から始めることにする。
普通のリトリーブ、早めのリトリーブ、リトリーブ中にアクションを追加。
三角波の先頭に虚しく羽ばたくシケイダー・・・。
スローに引いていくとポツリと空かしバイトが・・・、哀れ・・・(悲)
人の悪いばるたんさんが、この哀れなバイトを車から見た!と、
とてもタイミング悪く登場、計算だろうか?
ところで、シケイダーを投げていて気が付いたが、ガングリップの竿には意外なくらいマグVブレーキは感じが良い。
強く握らないでふわっと投げるキャストだと、スプールを加速している時間はビュンと投げるときの倍くらいはある感じ。
リリースから振り込んでいる間の竿が踏ん張れる感じが遠心ブレーキよりあるため『長く持っていられる感』が飛距離を生んでくれる。
シケイダーのブレーキは(5.5)、小刻みにブレーキ設定を変えられる気安さは安心感。
ブレーキダイアルの方向が、スコーピオンMgと逆で強くしようとして弱めたり・・・ってな失敗はあったが気付けば後は問題なし。
ブランクスルーの竿でマグVに感じていたモッタリ感や最後の伸びの無さは、飛距離を得ようとブンブン振るためにブレーキ設定が強めだったことも関係しているようだ。
今回は長く持ったようなスイングでじっくりと回転を上げるから、ブレーキ弱めでもキャスト直後のバックラッシュとは無縁。
その上弱めのブレーキ設定はマグのモッタリ感を弱め、キャスト後半はPEラインの風流れを押さえてくれて微妙なサミングもほとんどしなくて済んでしまう。
遠心とマグVのキャラクターの違いと言えばそれまでだが、
有効な活用法が今まで見えなかっただけにこれは収穫。
釣果の収穫は全然無いので、ルアーチェンジを繰り返しているとキッカケになるルアーが遂に出た。
イエローマジック 6cm (7gくらい)
ポコン、ポコン、とポップしていくとバイトが増え、
それに釣られたかのように周囲はライズの嵐に!!!
多少喰うには良くない大きさなのか?ヒットにはつながら無いが、魚たちの注意を一気に水面に引きつけた。
ファーストフィッシュまでの時間とゲームの時間
そこでDUELのチビポッパーに切り替えるとようやくヒット!
15:14、待望のファーストフィッシュ!

スタートから約50分!!
魚のたんまり入った管理釣り場で一尾を釣ると言う意味では、
『ずいぶんと長い時間だ。』
普通の人ならトップウォーター・プラグなんてとっくに諦めて
自信のある他のルアーを投げるだろう(笑)
「たった一匹釣るのにそんなに時間をかけて、
残り2時間ちょっとで何匹釣れるのさ?」
至って合理的な質問だろう。
「今日はこの一匹で終わりかも?(笑) わはは!」
今ならそう笑って答えられる。
他のルアーならともかく誰も投げていないようなルアーはここからが違う。
注意を一端水面に向けることさえ出来れば、そこからはかなり余裕で釣り続けられる事が多い。
ポップに激しくリアクションするのを確認して追試をしていく。
こうなると、2連続、3連続は当たり前。

他のルアーの適合具合を試し、本当にポップが良いか?を更に確認。
釣れたのは全部25cmくらいのニジマスOnly。
短く強いポップ、動く!止める!がハッキリするほどリアクションも強くなった。

ただし、明らかに釣れるようになるとゲームは終わり。
別に時間が来たワケじゃなく、30分も釣れ続ければゲームは段々と漁獲作業に近くなってしまうからだ。
最初の一匹を期待したあの感じはどこかに消える。
池がリセットされて初めて訪れた王禅寺だったが、実を言えば今回のパターンは旅人さんの釣行記から多少の予想はしていた。
同じ時間帯にほとんど同じ手順で進めたとはいえ、ルアーやアクションのパターンについては全く同じ結果に嬉しくなった。
特殊なスタイルで他の情報が当てにならないと書いたこともがあったが、それは既に遠い昔のことのようだ。
黄色のPixy+偽バンタムのフィーリング
キャストに関してはタックル自体が羽のように軽く、おかげで握りしめること無しにゆったり振れるバランスは、今までの組み合わせの中では抜群と言っても良い。
自己基準に「あれれ?」とマッチしてる
ヒット~フッキングの間に影響するギヤ比(1:5.8)も、ミリオネアST-1000(1:5未満)やカルカッタ50XT(1:5.0)からすると、忙しくなく25cmのトラウトが引っ張られてしまう分を充分に巻き取ってくれた。
竿でためすぎると口切れするのか?
竿をグイグイ曲げてやるとこれでもか!?というほどバラシを連発したが、竿の良い角度を見つけてこちらも解消。
作成時にニューガイドコンセプトとは異なるガイド間隔(曲げたい箇所を作るため)を設定した分、曲げすぎるとラインの角度が強くなる部分が効率を落とし、ある程度曲がるとハンドルからの入力でドラグが滑りやすいが、偽ELESEと同じブランクでもっと曲げたい設計思想なのでそこは仕方なし。
ELESEから始まりパワーを落とした偽ELESEの2つは、TBSリールシートを深く握ってブンブン振れるタックルだったが、ある意味力んで投げますよ!って前提からは逃れられなかった。
ブランクスルーのリールシートしかり、ニューガイドコンセプトしかり、ブランクのパワーを余すところ無く引き出す思想は、方向に関するコントロールをキッチリさせて、細身の軽いブランクを攻撃的に仕上げてくれた。
結果スイングを速くすることができて軽量系の飛距離は伸びたが犠牲にした部分もある。
利点ばかりを追っていたら、いつしかリリースポイントは限定的でルアー飛翔速度が速くて飛んでいる間が忙しい・・・という釣果を追うことばかりに向いた心理的な余裕を失っている部分。
黄色のPixy+偽バンタムのフィーリングは、まさしく今まで余裕の少ない自分を見直すだけの感触を与えてくれた。
ほんの5%くらいの飛距離と引き替えに、
力まずゆったり振れるための良さ。
リリースポイントが広いおおらかさ。
ゆっくり飛ぶ分サミングの緊張感の少なさ。
軽量トップウォーター・ゲームを楽しむための要素は、釣ること意外にもフィーリングを楽しむ部分はあると思う。

パターン構築プロセスも更にゆる~く楽しめそうです!
<最後に>
お忙しいところ現場まで見にきてくれたばるたんさん、いつもありがとう!
事前にアクションパターンを書いて下さった旅人さんに感謝!
そして、長文をいつも読んでくださるみんなに感謝!!
ほんとうにありがとう!
※ あくまで自己基準の旧式な仕様ですので、ブランクスルーでスタートした方には角度のあるグリップは相当の違和感があると思われます。
あほあほルアーマンの この記事のつづきを読む
2010年01月11日
黄色のPixy再び管理釣り場へ【久々登場】
あけましておめでとうございます。
久々登場はDaiwaのベイトなのか、三ツ木左右衛門自身なのか
区別が付きにくいのをどうかご勘弁下さい。<(_ _)>
前置き【Daiwaの小型ベイト】
’80年代前半、Daiwaのベイトキャスティングリールには大きく分けて3つの系統があった。
大きいミリオネア、小さいミリオネア、ファントム・・・・。
ABUの5000番台そっくりな大きいミリオネアは、三ツ木少年の手にも財布にも余る感じで選択肢ではなかった。
ファントムは当時最新鋭の高級機で、
少年の財布では諦めざるを得ない機種。
必然的に選択肢はファントムの半額ぐらいの「小さいミリオネア」であり、カタログ上の小さな一角に掲載された3機種くらいが目標だった。
身近な少年達も「小さいミリオネア」は妥当な現実だった。
安いクローズドフェイスからステップアップしたいのだから、ファントムの半額という価格に惹かれる。
なんたってプラグが根掛かりしたら泳いででも回収に行くような貧乏性なんだから・・・。
身近な釣り友達がミリオネアGS-1000~3000ユーザーになると、一緒に釣りに行って少し持たせてもらったりもした。
ようやく手に入れたミリオネアST-1000は、ベイトリールの重さもバランスもこれしか知らない状態で
コレが自己標準!!

最初に手に馴染むまで使った道具は、どうあがいてもそれが自己標準。
頭では忘れていても、体にガッチリ染みついている記憶。
長く自転車に乗っていなくても乗り方を忘れないような、そういう根っこの部分の説明しにくい暗黙知。
そんな自己標準を多分みんなそれぞれ持っている。
そして同じ感触にたまたま出会ったときに、「あれれ?」と甦る。
3年置き去りだった黄色のPixy
日付を見て愕然としたが、次のカンツリで使うと書いた黄色のPixyをアクシデントでラインを別のリールに巻き替えたため見送り、その後3年置き去りにしていたのを発見した。
もちろん忘れてはいなかったが、その後バス用に20lbPEを巻いたため管理釣り場に持ち込むことなく、新しい竿と他のリールの組み合わせを見ていて、そもそも釣りにあまり行かなくなったりが重なって気が付いたら3年の月日が経過していた。
当時、オリヂナルロッド作成に踏み切ったこともあり「タックルそのもののセッティング」を先にやってた事情もある。(偽ELESE)
そうこうする内、ガングリップの偽バンタムを製作し琵琶湖に持ち込む際に手持ちのリールを合わせてみて驚いた。
例の「あれれ?」が出てしまった。
【絵だけじゃ絶対分からない感触がもどかしい・・・】

20lbPEを巻いたのもあって飛距離は出なかったが、振り抜きの感触は安物のグラスロッドにミリオネアST-1000を乗せた感触を再び呼び起こす感じがした。
三日間使い倒してその感触を確認した。
次はもちろんミリオネアST-1000と偽バンタムを組み合わせてみた。
例の「あれれ?」は再現するのだろうかと。
ミリオネアST-1000のキャストフィールは驚くほどにポイントが掴みやすくてノスタルジーに浸れた。
1.2gのスプーンを苦しむことなく投げられたのに驚いた。
ただ、当時の竿とブランクが全然違うせいなのか?
リールのヒビが気になってビビりキャストなのか?
それとも記憶が美化されすぎているのか?
これはもう微妙な部分の確認はせずに
想い出の品が壊れる前に大事に仕舞っておくことにした。
ここからはリールの購入順で試していく。
カルカッタ50XTは90年代のバスブーム期に久々登場した小型ベイトで、一目惚れして(二台も)買って、長らく現役で使っていたものだ。
2005年末に管理釣り場のトラウトに使っていたが、王禅寺のモンスター戦頃からキャストフィールが悪くなって眠らせていたリール。
時空系チューニング【ベアリング減らし】で調子を取り戻してようやく使うことが出来た。
フィーリングについてはそこそこ良いが、比較相手がST-1000やPixyという極端に軽いリールと極端に軽い竿の組み合わせのバランスのせいか重さが気になった。(それでも50XTはたったの185g)
ST-1000やPixyの常にふわっと握っていられた感じが消えた。
そして管理釣り場のトラウトに使わなくなった理由を思い出すことに・・・。
金属リール冬は冷たすぎ・・・(以下中略...)
スコーピオンMg1000+偽バンタムはもっと馴染まなかった。
175gというスペックはカルカッタ50XTより馴染みそうに思えたし、同じブランクの偽ELESEでは素晴らしくマッチングしてるから、結構期待して持ち込んだのだ。
偽バンタムとのフィーリングは、
ガングリップのオフセットとサムバーの位置が合ってない。(ヒネリ感あり)
ノスタルジー風味付けのガイド間隔では遠心ブレーキの抜けが良すぎて竿が踏ん張る前にラインが出ていく感じがする(回転が上げられない)
メタマグ+偽バンタムは、なんと装着すら叶わなかった。
・・・と、ここでようやく一巡。
4lbPEにラインを巻き替えたPixy+偽バンタムの出番は近日中の予定。
ドラグのお題は・・・・、大きいのが掛からない限り判断不能である(笑)
6:3:1に美化された記憶
人間楽しく生きるために記憶を美化する脳の仕組みをTVで見た。
島田紳助の番組だったと思うがそこは定かじゃない。
脳に残る記憶の内、
6割は楽しい記憶
3割が辛い記憶
1割がその他の記憶・・・・だと。
短所すら長所に変換するポジティブシンキングがどこかで起こるのだろう。
そういう記憶の美化は悪い事じゃないが、昔々に手に馴染んだ道具を久しぶりに使ったときにギャップにガッカリするなんてのは良くあることだ。
Pixy+偽バンタムで、例の「あれれ?」を感じる幸運。
20年以上前のかなり美化された記憶に近い感触を得られる事自体とてもラッキーな事だと思う。
【ブランクとリールには20年分の進歩がある】

リールシートとベイトリールの関係
今でも良く中古屋で見かけるが、80年代後半にDaiwa独自のブランクスルーのリールシート(グレーのEVA)を手に入れた。
直線的な外観はともかく握った感じはオフセット感があり、力んで投げても真っ直ぐ投げられるブランクスルーのリールシートはすぐに気に入った。
何より安心だったのがリールを止める機構がしっかりしていたこと。
Fujiガングリップのような危うさがなく、コイン不要で装着がしっかり出来たことが進歩だった。
90年代に入るとFujiもどんどんブランクスルーのリールシートを発売して選択肢がぐんと広がった。
リール脱着が確実なのはもちろん、色々握って感触が良いのを選べる利点もあったが、ブランクスルー故にオフセット量が徐々に少なくなって今までのリールの腰高感が浮き彫りになってきた。
新しく発売されたリールはどんどんロープロファイル化して、リールフットはボディーにどんどん喰い込むのが主流になっていく。
ここら辺でベイトリールとリールシートの相性問題発生。
ベイトの竿とリールの組み合わせがパズルになったのがこの時期だ。
竿とリールが一体化しているベイトタックルならではの難しさ。
相性問題で上手く行かないリールもあるけど、中には守備範囲がとても広いリールもある。
手持ちの中で最も守備範囲が広いのが、この黄色のPixyなのだ。
全てにおいて最高ってワケではないが、どう組み合わせても「不可」にならないマルチプレイヤー。

ベイト難民村2008キャンプで集まったときに一番人気なことに驚いた。

並べてみたら黄色のPixyが三台・・・・。
次は一体何台並ぶのだろうか??(笑)
Daiwaか?shimanoか?それとも?
リール選びで最もよく見る葛藤はDaiwaとshimano どちらを選ぶのか?
中には「あなたは一体どっち党なのか?」と問う人もいるかもしれない。
自身の少年時代はDaiwa党だったけど、それはお小遣い防衛のため他メーカーの誘惑を断ち切る手段だったように思う。
初めてのshimanoベイトはカルカッタ50XTだったけど、当時のDaiwaに300g近いベイトリールしかなく、小型のベイトリールの魅力にまいってしまった。
どこのメーカーが作ったかよりも、
どのくらい要求やら欲求を満たしてくれるか?
使えないギミックを廃し、軽くコンパクトに仕上がったカルカッタは当時のエポックメイキングだった。
Daiwa以外にもABUから乗り換えた人も多かったんじゃないかな。
周囲でも久しぶりに会った釣友達がいつの間にかカルカッタを持っていた。
カルカッタの遠心ブレーキ(SVS)は意外なくらい好感触で驚いたけど、こいつの泣き所はブレーキ変更する仕組みだ。
カルカッタ50XTはスプールまで外さないとブレーキ変更が出来なかったのだ。
この時はブレーキ設定の違うタックルをもう一組用意するという、釣具屋さん大喜びなチカラワザでごまかした。時代だよね・・・この辺は。
今でもブレーキの仕組みの違いがDaiwaかshimanoのどちらを買うかの最大のポイントになってるのは間違いないんだけど、使う段階ではリールを乗せたときのバランスについついうるさくなってしまうし、できれば蓋を開けずにブレーキ変更したい。
次のエポックメイクなリールはどのメーカーから出るのだろうか?
とにもかくにも、軽量キャストを風の中でもすることになる軽量小型ベイトリールにはただでさえ要求事項が多い。
ガングリップの偽バンタムにようやく一巡して乗ることになった黄色のPixy
どんなフィーリングを見せてくれるのか楽しみだ。
久々登場はDaiwaのベイトなのか、三ツ木左右衛門自身なのか
区別が付きにくいのをどうかご勘弁下さい。<(_ _)>
前置き【Daiwaの小型ベイト】
’80年代前半、Daiwaのベイトキャスティングリールには大きく分けて3つの系統があった。
大きいミリオネア、小さいミリオネア、ファントム・・・・。
ABUの5000番台そっくりな大きいミリオネアは、三ツ木少年の手にも財布にも余る感じで選択肢ではなかった。
ファントムは当時最新鋭の高級機で、
少年の財布では諦めざるを得ない機種。
必然的に選択肢はファントムの半額ぐらいの「小さいミリオネア」であり、カタログ上の小さな一角に掲載された3機種くらいが目標だった。
身近な少年達も「小さいミリオネア」は妥当な現実だった。
安いクローズドフェイスからステップアップしたいのだから、ファントムの半額という価格に惹かれる。
なんたってプラグが根掛かりしたら泳いででも回収に行くような貧乏性なんだから・・・。
身近な釣り友達がミリオネアGS-1000~3000ユーザーになると、一緒に釣りに行って少し持たせてもらったりもした。
ようやく手に入れたミリオネアST-1000は、ベイトリールの重さもバランスもこれしか知らない状態で
コレが自己標準!!

最初に手に馴染むまで使った道具は、どうあがいてもそれが自己標準。
頭では忘れていても、体にガッチリ染みついている記憶。
長く自転車に乗っていなくても乗り方を忘れないような、そういう根っこの部分の説明しにくい暗黙知。
そんな自己標準を多分みんなそれぞれ持っている。
そして同じ感触にたまたま出会ったときに、「あれれ?」と甦る。
3年置き去りだった黄色のPixy
日付を見て愕然としたが、次のカンツリで使うと書いた黄色のPixyをアクシデントでラインを別のリールに巻き替えたため見送り、その後3年置き去りにしていたのを発見した。
もちろん忘れてはいなかったが、その後バス用に20lbPEを巻いたため管理釣り場に持ち込むことなく、新しい竿と他のリールの組み合わせを見ていて、そもそも釣りにあまり行かなくなったりが重なって気が付いたら3年の月日が経過していた。
当時、オリヂナルロッド作成に踏み切ったこともあり「タックルそのもののセッティング」を先にやってた事情もある。(偽ELESE)
そうこうする内、ガングリップの偽バンタムを製作し琵琶湖に持ち込む際に手持ちのリールを合わせてみて驚いた。
例の「あれれ?」が出てしまった。
【絵だけじゃ絶対分からない感触がもどかしい・・・】

20lbPEを巻いたのもあって飛距離は出なかったが、振り抜きの感触は安物のグラスロッドにミリオネアST-1000を乗せた感触を再び呼び起こす感じがした。
三日間使い倒してその感触を確認した。
次はもちろんミリオネアST-1000と偽バンタムを組み合わせてみた。
例の「あれれ?」は再現するのだろうかと。
ミリオネアST-1000のキャストフィールは驚くほどにポイントが掴みやすくてノスタルジーに浸れた。
1.2gのスプーンを苦しむことなく投げられたのに驚いた。
ただ、当時の竿とブランクが全然違うせいなのか?
リールのヒビが気になってビビりキャストなのか?
それとも記憶が美化されすぎているのか?
これはもう微妙な部分の確認はせずに
想い出の品が壊れる前に大事に仕舞っておくことにした。
ここからはリールの購入順で試していく。
カルカッタ50XTは90年代のバスブーム期に久々登場した小型ベイトで、一目惚れして(二台も)買って、長らく現役で使っていたものだ。
2005年末に管理釣り場のトラウトに使っていたが、王禅寺のモンスター戦頃からキャストフィールが悪くなって眠らせていたリール。
時空系チューニング【ベアリング減らし】で調子を取り戻してようやく使うことが出来た。
フィーリングについてはそこそこ良いが、比較相手がST-1000やPixyという極端に軽いリールと極端に軽い竿の組み合わせのバランスのせいか重さが気になった。(それでも50XTはたったの185g)
ST-1000やPixyの常にふわっと握っていられた感じが消えた。
そして管理釣り場のトラウトに使わなくなった理由を思い出すことに・・・。
金属リール冬は冷たすぎ・・・(以下中略...)
スコーピオンMg1000+偽バンタムはもっと馴染まなかった。
175gというスペックはカルカッタ50XTより馴染みそうに思えたし、同じブランクの偽ELESEでは素晴らしくマッチングしてるから、結構期待して持ち込んだのだ。
偽バンタムとのフィーリングは、
ガングリップのオフセットとサムバーの位置が合ってない。(ヒネリ感あり)
ノスタルジー風味付けのガイド間隔では遠心ブレーキの抜けが良すぎて竿が踏ん張る前にラインが出ていく感じがする(回転が上げられない)
メタマグ+偽バンタムは、なんと装着すら叶わなかった。
・・・と、ここでようやく一巡。
4lbPEにラインを巻き替えたPixy+偽バンタムの出番は近日中の予定。
ドラグのお題は・・・・、大きいのが掛からない限り判断不能である(笑)
6:3:1に美化された記憶
人間楽しく生きるために記憶を美化する脳の仕組みをTVで見た。
島田紳助の番組だったと思うがそこは定かじゃない。
脳に残る記憶の内、
6割は楽しい記憶
3割が辛い記憶
1割がその他の記憶・・・・だと。
短所すら長所に変換するポジティブシンキングがどこかで起こるのだろう。
そういう記憶の美化は悪い事じゃないが、昔々に手に馴染んだ道具を久しぶりに使ったときにギャップにガッカリするなんてのは良くあることだ。
Pixy+偽バンタムで、例の「あれれ?」を感じる幸運。
20年以上前のかなり美化された記憶に近い感触を得られる事自体とてもラッキーな事だと思う。
【ブランクとリールには20年分の進歩がある】

リールシートとベイトリールの関係
今でも良く中古屋で見かけるが、80年代後半にDaiwa独自のブランクスルーのリールシート(グレーのEVA)を手に入れた。
直線的な外観はともかく握った感じはオフセット感があり、力んで投げても真っ直ぐ投げられるブランクスルーのリールシートはすぐに気に入った。
何より安心だったのがリールを止める機構がしっかりしていたこと。
Fujiガングリップのような危うさがなく、コイン不要で装着がしっかり出来たことが進歩だった。
90年代に入るとFujiもどんどんブランクスルーのリールシートを発売して選択肢がぐんと広がった。
リール脱着が確実なのはもちろん、色々握って感触が良いのを選べる利点もあったが、ブランクスルー故にオフセット量が徐々に少なくなって今までのリールの腰高感が浮き彫りになってきた。
新しく発売されたリールはどんどんロープロファイル化して、リールフットはボディーにどんどん喰い込むのが主流になっていく。
ここら辺でベイトリールとリールシートの相性問題発生。
ベイトの竿とリールの組み合わせがパズルになったのがこの時期だ。
竿とリールが一体化しているベイトタックルならではの難しさ。
相性問題で上手く行かないリールもあるけど、中には守備範囲がとても広いリールもある。
手持ちの中で最も守備範囲が広いのが、この黄色のPixyなのだ。
全てにおいて最高ってワケではないが、どう組み合わせても「不可」にならないマルチプレイヤー。

ベイト難民村2008キャンプで集まったときに一番人気なことに驚いた。

並べてみたら黄色のPixyが三台・・・・。
次は一体何台並ぶのだろうか??(笑)
Daiwaか?shimanoか?それとも?
リール選びで最もよく見る葛藤はDaiwaとshimano どちらを選ぶのか?
中には「あなたは一体どっち党なのか?」と問う人もいるかもしれない。
自身の少年時代はDaiwa党だったけど、それはお小遣い防衛のため他メーカーの誘惑を断ち切る手段だったように思う。
初めてのshimanoベイトはカルカッタ50XTだったけど、当時のDaiwaに300g近いベイトリールしかなく、小型のベイトリールの魅力にまいってしまった。
どこのメーカーが作ったかよりも、
どのくらい要求やら欲求を満たしてくれるか?
使えないギミックを廃し、軽くコンパクトに仕上がったカルカッタは当時のエポックメイキングだった。
Daiwa以外にもABUから乗り換えた人も多かったんじゃないかな。
周囲でも久しぶりに会った釣友達がいつの間にかカルカッタを持っていた。
カルカッタの遠心ブレーキ(SVS)は意外なくらい好感触で驚いたけど、こいつの泣き所はブレーキ変更する仕組みだ。
カルカッタ50XTはスプールまで外さないとブレーキ変更が出来なかったのだ。
この時はブレーキ設定の違うタックルをもう一組用意するという、釣具屋さん大喜びなチカラワザでごまかした。時代だよね・・・この辺は。
今でもブレーキの仕組みの違いがDaiwaかshimanoのどちらを買うかの最大のポイントになってるのは間違いないんだけど、使う段階ではリールを乗せたときのバランスについついうるさくなってしまうし、できれば蓋を開けずにブレーキ変更したい。
次のエポックメイクなリールはどのメーカーから出るのだろうか?
とにもかくにも、軽量キャストを風の中でもすることになる軽量小型ベイトリールにはただでさえ要求事項が多い。
ガングリップの偽バンタムにようやく一巡して乗ることになった黄色のPixy
どんなフィーリングを見せてくれるのか楽しみだ。
あほあほルアーマンの この記事のつづきを読む